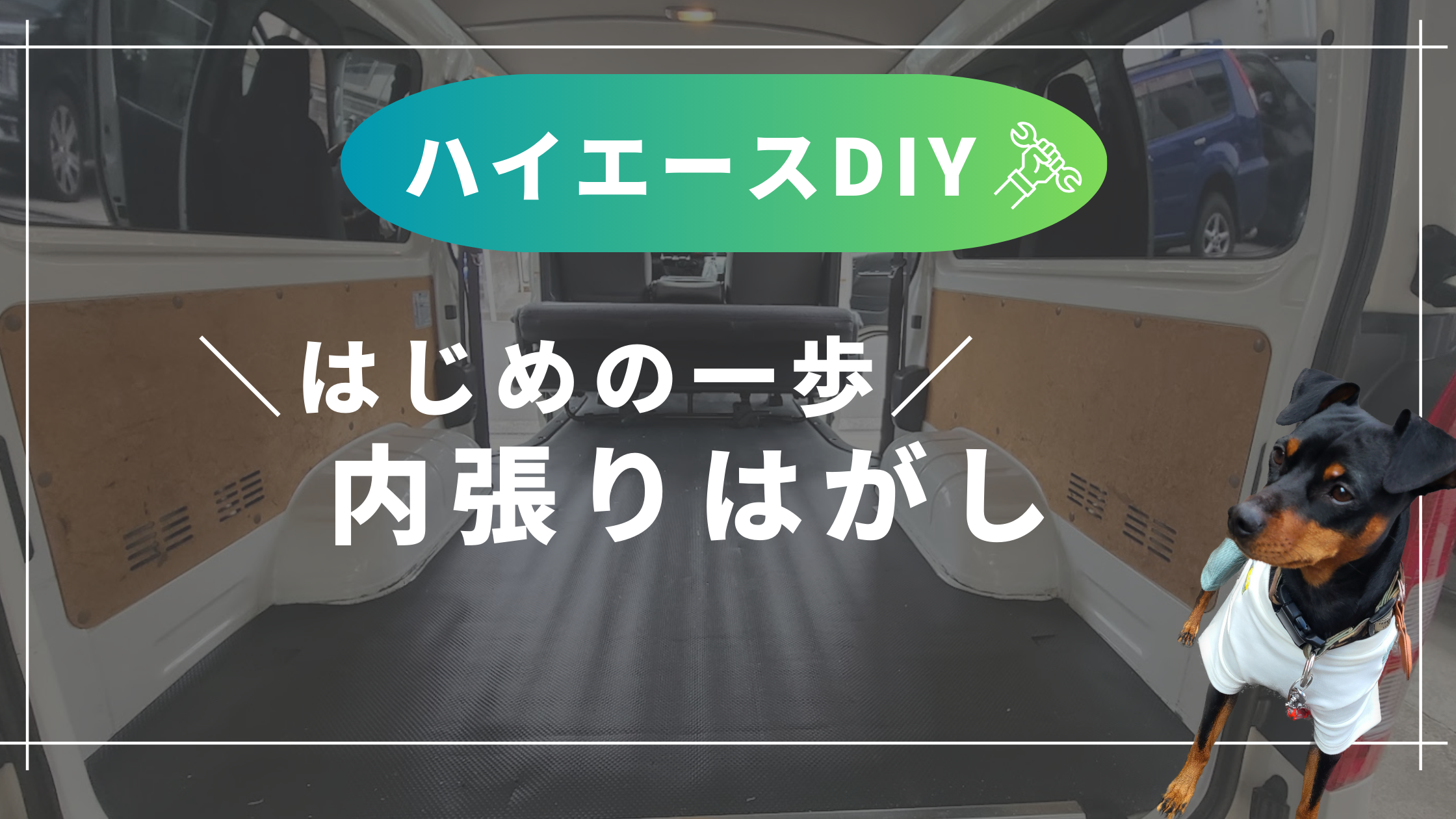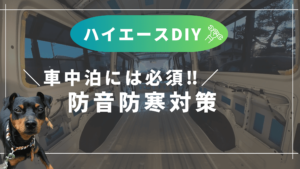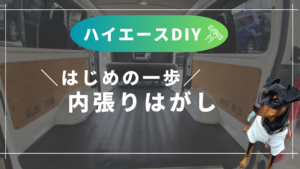犬連れ30代夫婦、ハイエースを車中泊仕様にDIYし日本半周を終了しました。




1年間DIYしたハイエースに乗車し、無事に車検も通過しています。
- ハイエース内を車中泊仕様に改造したい
- DIY素人でも簡単にできるのだろうか?
- まず何から始めたら良いのだろう?
DIY素人でも簡単に、車体に穴を空けずに改造した方法を紹介します。
ハイエースDIYの最初は、内張り・天井を剥がすことです。







この工程は半日~1日で終了します。




作業開始前にするべき、4つのことも紹介していきます!
- ハイエースの内張りはがしに必要な材料リストが分かる
- 費用や作業時間が分かる
- 実際に体験した失敗談




DIY素人の夫婦、ハイエース改造は失敗もありました。
みなさんは失敗しないように、最後までご覧下さい!



ハイエースDIYを始める前の準備
内張り剥がし~防音防寒対策~運転できる状態に戻すまで早くても1週間ほどかかります。
車を使えなくなるため、スケジュール調整や買い物を済ませておきましょう!
- 車を使う予定は入れない
- 1週間分の買い物は済ませておく
- 晴れが続く日を狙う
- 作業材料の買い忘れがないかチェックしておく




ペンキを買いに行きたいのに、車が使えない…




自転車で頑張るしかない…
そんな状態にならないように、事前準備は大切です。病院や友人との予定も調整しておきましょう。
ハイエースDIYの手順を紹介していきます。
DIY最初は内張り&天井剥がし



ハイエースを車中泊仕様にDIYするために、内装を一度撤去します。
【内装を撤去する順番】
- 後部座席の撤去
- 床のマット撤去
- 内張りはがし
- 運転席の撤去
- 天井はがし
内張りとは、車内の左右に張られている茶色い板です。







中古車の場合、錆も取る必要があります。




綺麗に清掃することで、断熱材、防音材が密着し長持ちします。
それぞれの工程と、各作業ポイントを紹介していきます。
【ハイエースDIYの第一歩】①後部座席を撤去する



ブラスドライバーと、ラチェットレンチ14㎜を使用し、後部座席を取り外します。




実は、後部座席のネジは「固いくて回らない」とDIY界隈で有名な話です。




力の弱いDIY初心者主婦でも、最大限の力が発揮できる工具が必要…
ポイントは持ち手の長さ!
最小限の力でネジを回すには、取っ手の長いものを選びましょう!
車のDIYには14㎜のソケットが必需品です。
【ハイエースDIYの第一歩】②床マットの剥がし方



床のマットは敷いているだけなので、簡単に剥がせます。



スライドドアを開けた、ステップ部分のマットも剥がします。




クリップで付いているので、引っ張っれば簡単に外れます!
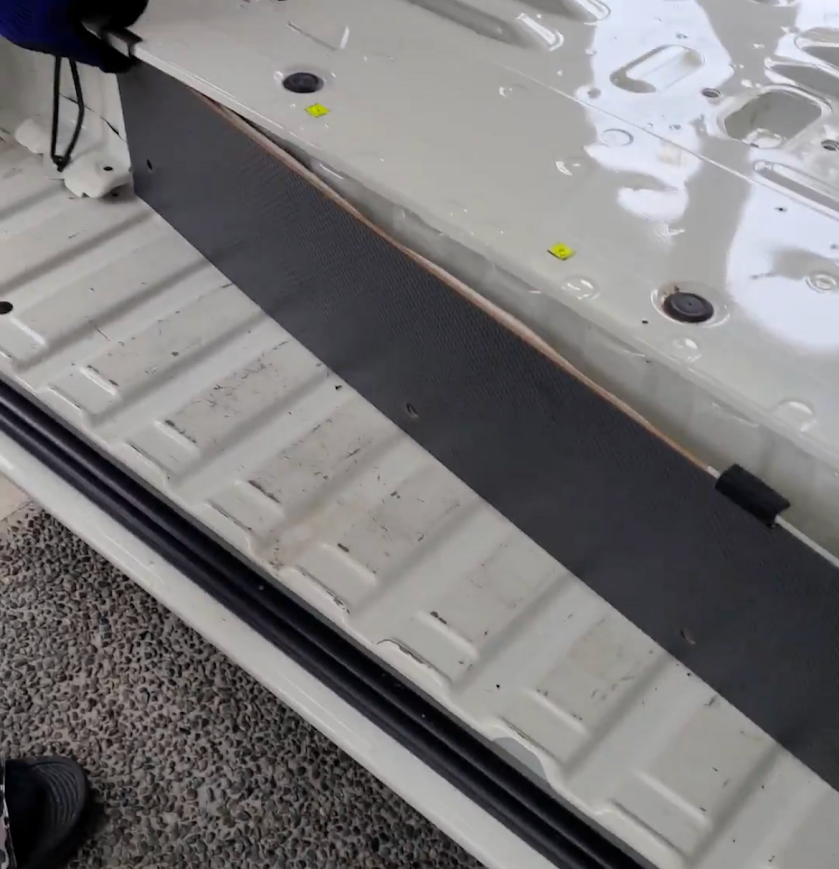
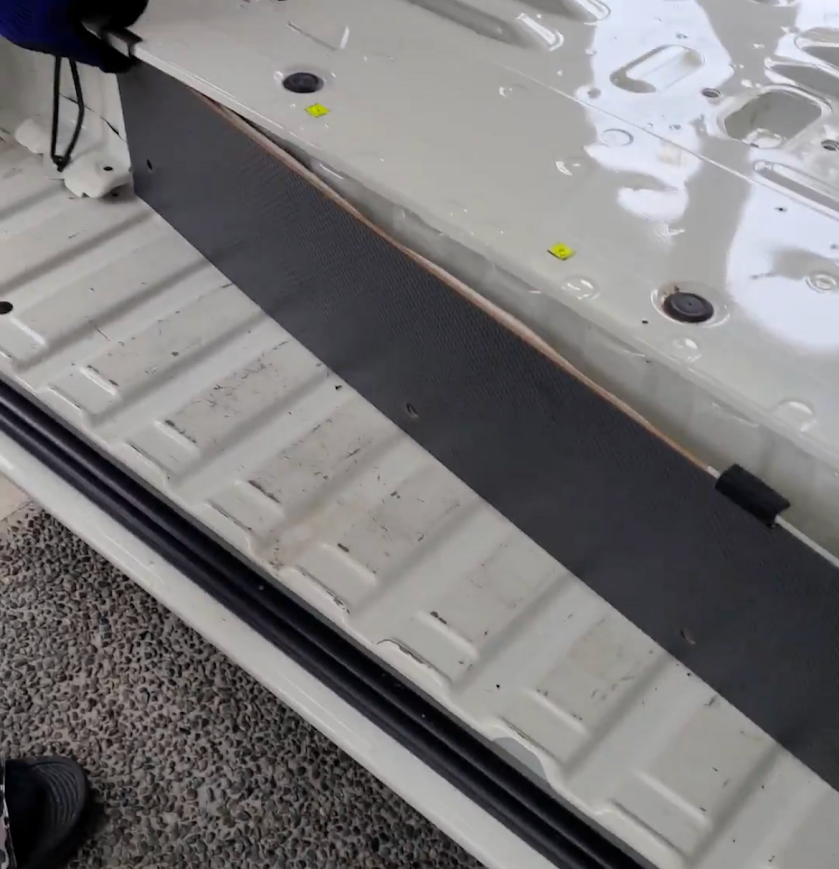
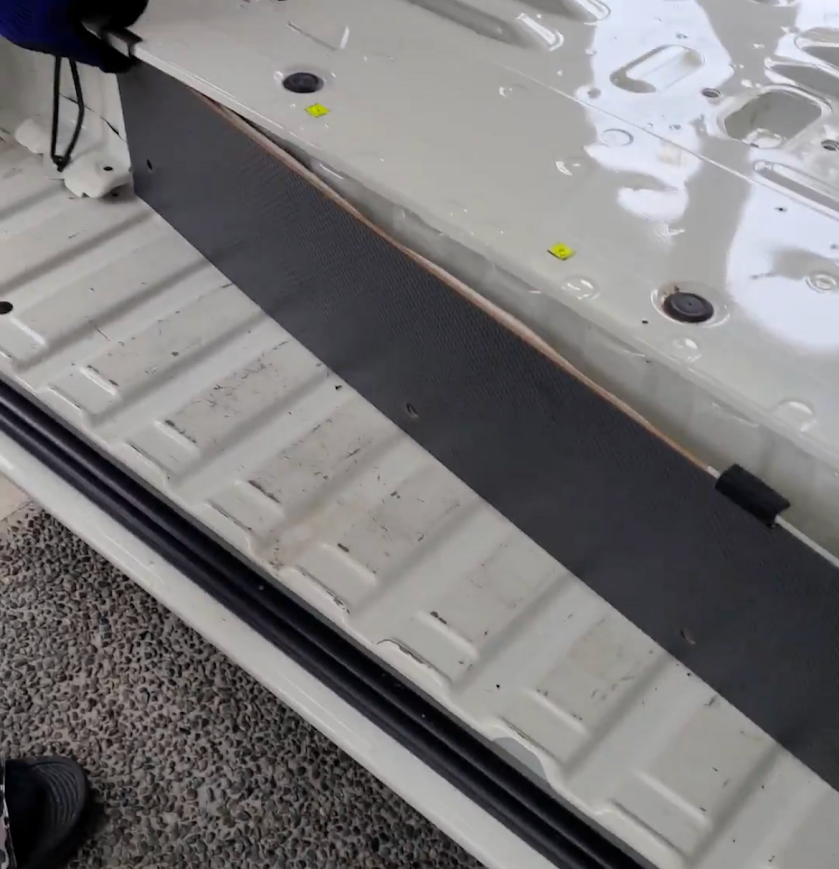
床のマットは全て剥がしました。
【ハイエースDIYの第一歩】③内張り剥がしの方法



内張はがしは、専用の工具が必要です。
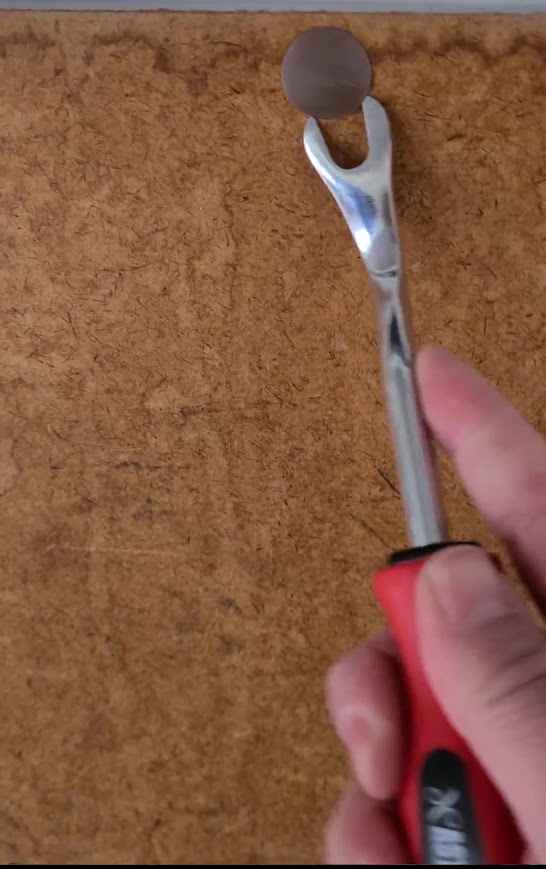
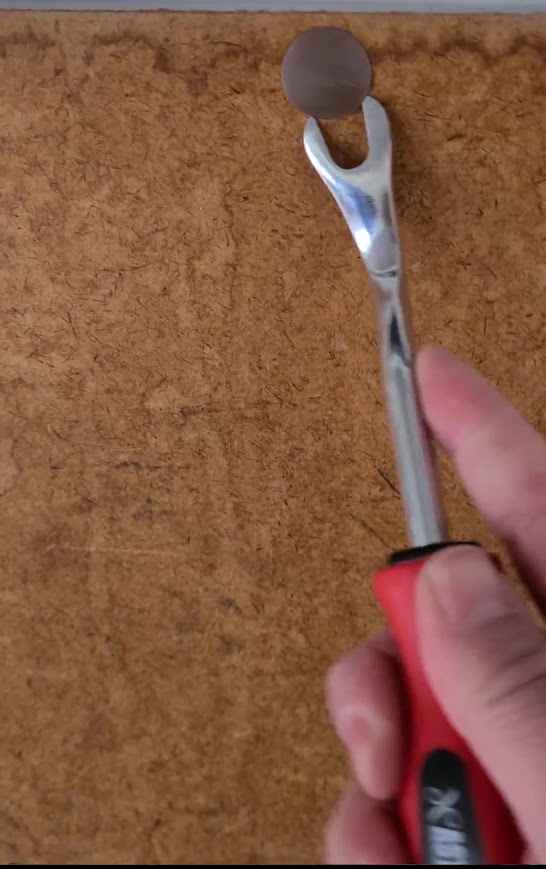
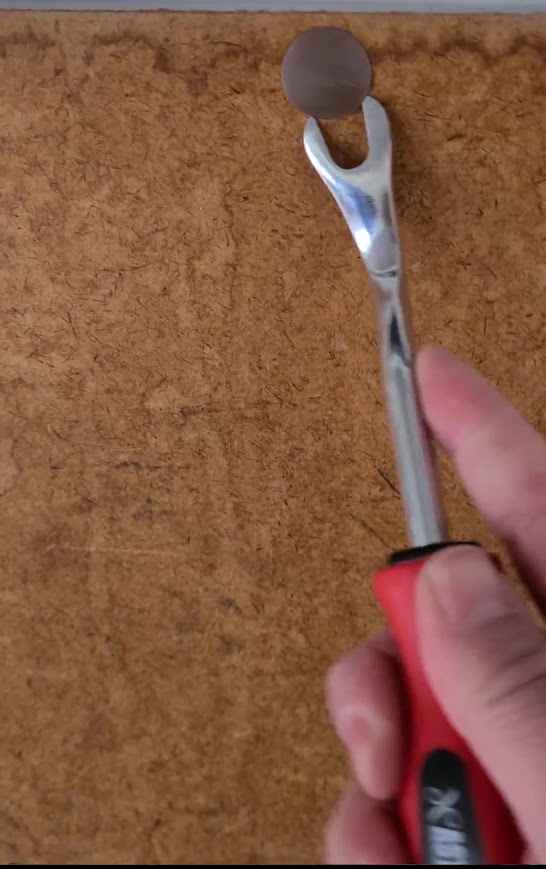
テコの原理でスポっと抜いていきます。内張り剥がしで取った部品は、また戻すので紛失しないようにしてください。




力づくで抜くと、部品が折れたり、どこかに飛んで行ったりするので注意。




剥がした部品、数個なくしてしまった…
1,500円前後で手に入るので、これからハイエースをDIYして車中泊旅をしたい人には必需品になります!
ハイエースDIY必須工具
内張り剥がしの手順を紹介していきます。
内張り剥がしか、マイナスドライバーでシートベルトのカバーを剥がします。
ラチェットでボルトを外し、シートベルトを撤去します。















内張り剥がしの工具を使い、留め具を外していきます。




無理やり留め具を引っ張り、いくつか割ってしまいました。




留め具は割れても、オートバックスで売ってたから大丈夫!






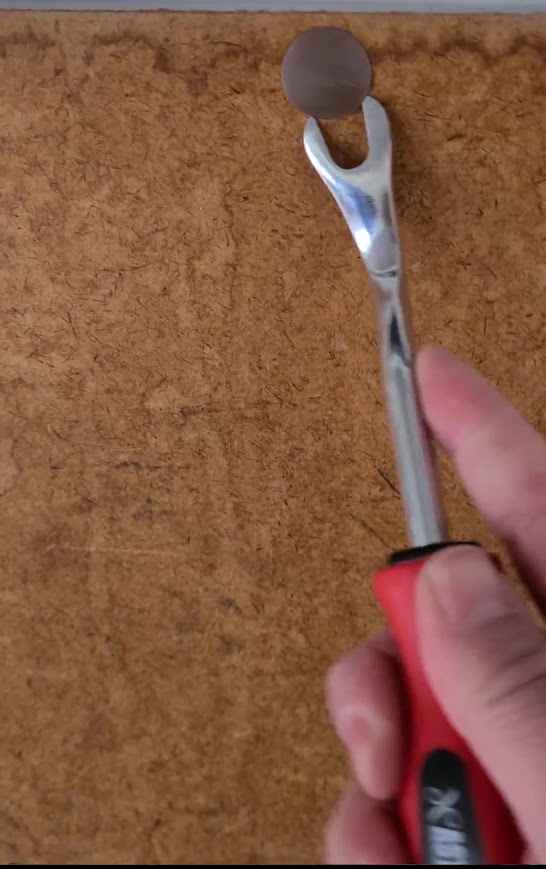
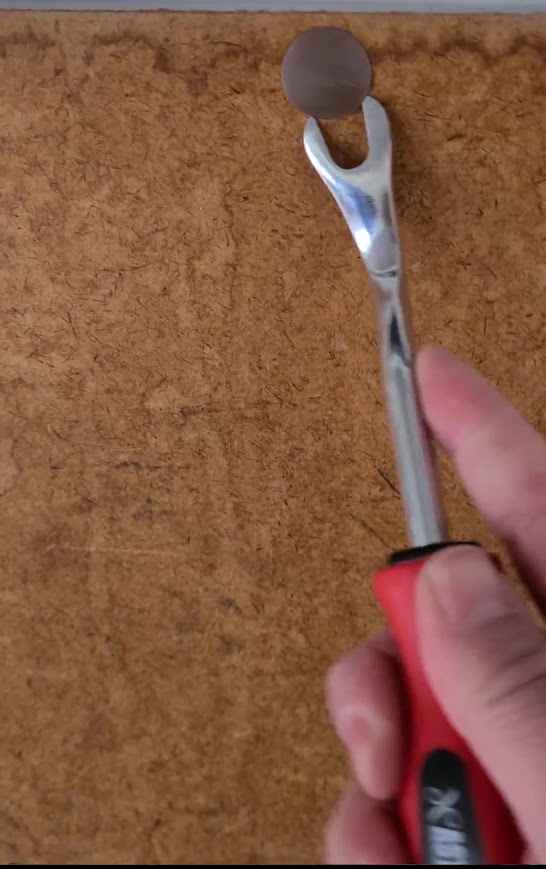
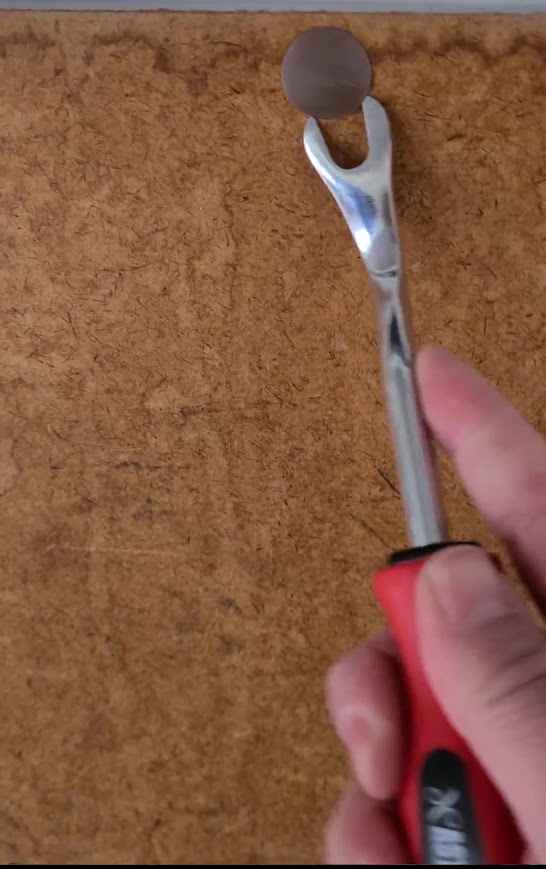
スライドドアも後部座席と同様に、板を外します。
半透明のフィルムは、手で剥がします。(我が家のハイエースは手動ドアです)









だいぶ露骨な状態になってきました。




まだまだこれからが本番です!
【ハイエースDIYの第一歩】④運転席の取り方



ネジを取って剥がします。
運転席周り、足周りののマットも剥がします。



【ハイエースDIYの第一歩】⑤天井の剥がし方



天井に着いている部品を全部剥がしていきます。
マイナスドライバーや、内張り剥がしで手すりを取っていきます。



プラスドライバーで外します。



手で簡単に剥がれます。



ライトも取り外します。
さいごに
簡単な作業工程で内張り剥がしが完成です!
作業工程
- 床のマット剥がし
- 内張り剥がし
- 運転席を取る
- 天井を剥がす
ドライバー、レンチ、内張り剥がしがあれば2時間ほどで作業完了です!
続いて、車内の防音防寒対策をしていきます!